うちの「春期講習」を受講すれば必ず成績が上がります?それ、ホンマでっか?♬♪♪♪~
★3月31日、最近、掲載がまた途絶えがちな中、たくさんのアクセスをいただきありがとうございます。「講習会」の内容の記事を見た方が多かったようですので、今回は、「春期講習」や「入塾時の面談の際の講師の言い回し」「新中1生の初めての定期テスト」について軽く触れたいと思います。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
塾の研修で、面談で絶対に言ってはいけない言葉を覚えさせられる…その代表的なものが、「必ず合格できます」「必ず成績が上がります」や。
考えれば分かるが、「一部のデキのええ生徒が通っとる」「あそこのセンセがええんやって」…評判をもとに塾選びをしても、自分の子供がデキが良くなるかどうか、評判のセンセのクラスに当たるかどうかなんて分からんやん。
その代わりに塾のセンセは、「私たちの言うとおりに勉強して、成績ごっつ上がった生徒ぎょうさんおりまっせ」とのたまう。つまり、それは、「塾を休まず」「授業を真剣に受け」「宿題を毎回し」「小テストを本気で受け」「講習会にも参加」すれば、成績が上がる可能性がより大きなりますよ、というこっちゃ。
春休みも半分過ぎた。みんなも、塾の「春期講習」に行っとるんやろな。なかには、自分で勉強でける「強者」もいるかもしれん。自分は、中学のときは、塾に通ってる時間や授業時間の無駄が嫌で途中でやめてもうたけど…。それでも、やっぱり、自分の知らん知識や解き方を教えてもらえたのはデカかったで。
「少しでも子供の力になれば…」「少しでも成績が上がれば…」と言う親の目論見ちゅうんは…少なからず失敗に終わることが多い、
なぜか?
考えてみて欲しい。多くの生徒が「春期講習」に参加する。
ちゅうことは、勉強が得意な生徒は今まで以上に伸び、勉強が苦手な生徒、好きではない生徒は、新学年度で「どんな勉強が始まるか」が少しは分かるようになる、ということになる。「その生徒に合わせた指導」「レベル別クラス編成」とはそういうもんやで。
これでは、「偏差値」や「内申」の差はぜんぜん縮まらんのは明白よな。今まで分からなかったことが分かる(自力で解けるようになる、ということはない)のは、大変よいことではあるが、「デキるやつ」は、春期講習を受けること(受けなくてもいい生徒ももちろんいる)でさらに難しい問題にチャレンジし、ぐんぐん伸びる。
特に、「春期講習」の位置づけを考えると、ここで「成績を伸ばす」というよりも「楽しさ」を伝える塾が多いんや。「塾側」としては、4月以降も継続受講してもらう、1年間この塾で勉強して欲しい、そのためには、まず、この時期「楽しさ」ちゅうわけや。
もともとその塾にいる生徒たちは「中学準備コース」なるものを受講し、「新中1」の春期講習」を受け、4月に「学校」と「塾」で勉強をし、塾の「定期テスト対策授業」なるものを受けて、初めての「定期テスト」を受けるんや。こんなに長い時間、繰り返し「同じ範囲」を勉強することは、まず、ないで。
もし、新中1のお子さんで、「5月6月」実施の「定期テストⅠ」が英語「80点」を割っていたり、数学「50点」を割っていたら…「春期講習」から4月・5月の「塾通い」の効果はあまりなかったと思ってええんやないかな。この「中1」の「1回目の定期テスト」、世間では「初めての定期テスト」だから「スタートでつまづかないことが大切」ちゅうことがよくうたわれる。
でも、それ以外の理由でも、実はむっちゃ大切なんよ。「中学受験」しなかった生徒たちは、勉強に対する「意識改革」が必要なんや。
英語は「小学生の復習」はもちろん、今まで「音読ができた」文を、今度は、テストで「正確に書く」ことが要求される。数学は、「小学生の復習」+「計算の基本(青婦の数の四則計算や文字式の計算)」が中心になる。
英語では、「書く」という「大きな壁」をぶち破る必要があるんや。「単語」を「書く」のとは別に「文を書くルール」を守らなアカんようになる。「発音」と「つづり」とのギャップや、「英文の語順(疑問文やwh疑問文の作り方なども含む)」に注意し、「先頭を大文字で」書き、文末に「.」や「?」をつける。文末の「.」や「?」を忘れるだけでも「×」になる。どうも生徒たちは、日本語にも「、」や「。」があることを棚に上げて、「わけわからんルール」を覚えなアカんと思いこんでいるようや。「書く」のが苦手で「英語嫌い」になる生徒も爆誕しだす。「リスニング」がどんなに得意な生徒でも、「書く」ことが苦手な生徒は点数を落とすことになる。特に解答欄には、「短い受け答え」、例えば、「昨日」と答える場合でも「Yesterday.」と「文頭は大文字」「ピリオド」を忘れれば「×」になる。
もし、数学で「文字式」が「定期テストⅠ」に出題されている場合、今、「文字式」の点数が悪くてもあまり気にすることはない。それよりも、「正負の数」の複雑な四則計算が満点であることが望ましい、と自分は思うで。学校によっては「東京都などの有名私立高校の入試級」の計算問題が出題される。回りくどい言い方をしてカンニンな、地方では「道立」や「県立高校」の方が「私立高校」より「上位校」だったりするんでな。実は、学校から渡される「教科書ワーク」にもある程度のレベルの入試問題が載っとる。「文字式」は、「方程式」「関数」や「図形」の分野でも出てくる。「代入」や「移項」などを経験し、慣れてくれば、「文字式」を使えるようになる生徒も結構おる。もちろん、「計算せよ」と「方程式を解け」などのちがいはしっかり押さえる必要があるけどな。
塾の話に戻そう。児童や生徒だっていろんなタイプがいる。例えば、「ライバル」がいる方が燃える生徒や積極的に授業に参加したい、人数が多い教室の方が勉強しやすい生徒の場合、親がよかれと思って「少人数」のクラスに入れてまうと、「恥ずかしがったり」「手元をみられたくなかったり」「発言や質問を控えたり」することがある。意外とよく面談で質問される「先生との相性」「宿題の多さ」以外の原因で成績が伸びない生徒もおることは親御さんにも知っておいて欲しい。
それでも、「春休み」を終えると、急に成績が伸び出す生徒も中にはおる。
やはり、最終的には、自分が、入試に出題されるような問題が「時間内」で「正確」に「自力」で「解けるか解けないか」よね。自分が今までできなかった問題、苦手な問題をどれだけ速く正確にできるようになったかが大事なんや。先生がそばにいればデケる、ではあかんのや。
テストでは、自分が分かる、解ける問題だけが出題されるわけではない。テスト範囲を全部勉強したからと言って、全問「解答」できるわけではないのだ。
塾の授業の時間では当然、すべてを教えるには短すぎるし、逆に自分が「1日何時間勉強したか」という勉強時間の長さだけではどうにもならんこともある。1冊の問題集を「10周」したって、答えを「丸暗記」しているのでは「入試問題」に対応できない。このタイプの生徒は「昨日、去年の過去問、ウチ、90点だったよ」とよく言う。が、「同じレベル」の別の問題を解かせても全然解けない場合が多い…。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
そうそう、春と言えば…見慣れた「C」のマークが今年も躍った甲子園。「智辯和歌山」は惜しくも決勝で敗れた。6回裏、「横浜高校」の攻撃、先頭打者がレフト前ヒットで出塁。続く打者がセンター前ヒット。これでノーアウト1塁2塁。ここで、次の打者は、「送りバント」ではなく、積極的に打ちに行く。打球はマウンドで跳ね、方向が変わる。これが、結果的には「智辯和歌山」にはラッキーな結果となる。ショートがセカンドベース付近でうまくさばきゲッツー。これで、2アウト3塁となる。あと一人でこの回を乗り切れる。ここで、智辯和歌山のエースが投じた球が、デッドボールになってしまう。この瞬間から流れが変わった。その後、タイムリーを浴び、「横浜高校」がペースを完全に握ってしまう。結局、9回を終えた時点では実力以上の大差がついてしまった。これが、一発勝負の「甲子園」の恐ろしさなんやね…。
まさに、その1球から試合の流れは変わる。フォアボール、デッドボール、エラー、バントミス…受験で言えば、「取れる問題をはずす」「計算ミスをする」「時間配分のミスをしてしまう」「問題文や選択肢の読み間違いをする」「マークミスをしてしまう」ことに近いかな…受験も一発勝負やから…その一つの勘違いやミスで「合否」が決まってしまう場合もある。
例えば、ピアニストがステージで演奏する際、ステージ慣れしている「演奏家」でも、実際に本番、「頭が真っ白」になってしまうことがある。
…こういう状況で「弾き続けられるピアニスト」と「手が止まってしまうピアニスト」の違いは何か…
これを説明するのは、難しい。でも、「子供の発表会」でも「手が覚えていた」「体が勝手に動いた」「集中して何とか乗り切った」というような表現を耳にする。
「だから、練習こそすべてだ」、と多くの人が言うんよね。練習の時に、ただ「20回弾く」のではなく、自分の音を聞き、時に録音し、楽譜と突き合わせて表現を分析し、難しい箇所をさらい、その前後と自然につながるまで練習する。それでも、本番「完璧」に演奏できる保証はない。練習も本番までの「時間」との戦いである。経験を積むと、より短い時間で準備ができるようになる。
英語を「読み(黙読)」「訳し」「声に出し(音読)」「書き」「間違えやすい文」や「単語の活用やその単語の例文」を調べ、覚える…
数学で「例題を解き」「練習問題を解き」「学校指定の問題集(学校の教科書ワーク)を解き」「自分の持っている問題集を解く」「間違えた問題に再度挑戦する・最短時間を設定し解くスピードを上げる」…
…たいていの生徒は「時間がない」ことを理由にどこかで止まっている。スポーツや芸術が優れているのは「遺伝」や「才能」だ、というのであれば、当然、勉強にも人によって「遺伝」の影響や「才能」の違いはあるはずや。
昔、数学で教師が「これがデキるとすごい」と言う問題にテスト中こだわり、その1問だけ正解した生徒がいたんや…点数は平均点を大幅に下回り、30点以下だった記憶がある…
…「悪い」とは言わん。こういう「生徒」を伸ばすのも大切やとわかっとる、でも、「入試」は待ってくれん。意識を変えてくれな間に合わん…数学のテストでは、「これはみんなできるでしょう」と言う問題が必ず載っている。定期テストであれば、まずは、「テスト範囲」全体の教科書に載っとる「例題・類題」「練習問題」「章末問題」が速く正確にできるようにしたらええ。それが「点数」を増やすことになる「正攻法」や。
もちろん、ピアニストだけではなく、他の芸術分野でもスポーツの世界でも、勉強というカテゴリーでも、練習やたいした勉強をしなくてもできてしまう、一握りの「天才」もいる。
まずは、自分は、勉強の「神」に選ばれし人か否か、と心に問うてみることやね。もちろん、自分もちゃうよ。中学校からは「勉強」せなできない人間側やったからな。勉強嫌いやったし。悔しい思いもたくさんした。
あと1回、「復習」をすればデキる問題、「宿題」に取り組めば「もう1問」デキる時間の余裕を手に入れることがデキるようになる、そんな問題をクリアーすることが「春」の勝敗を左右する。「前の日に習った問題なのにできなかった」「時間がなかった」と定期テストや模試の後に言わない、そんな自分を今日から「つくりあげる」ことや。
入試では、さらに、「時間内に解く」というおおきな条件がついてくる。
後は、キミがどれくらい「本気」で塾の授業に取り組むかだけだ。「アイツみたいにデキるようになりたい」「頭いいヤツはいいよな」…悪いが、その「熱い思い」だけでは、その子に追いつくことは限りなく「不可能」や。
問題文をしっかりと読み、手を動かし、ミスを少なくし、家で復習をし、「宿題」を自力でする。できない問題は、「塾」の先生をつかまえて聞く。「小テスト」を全力で満点取りに行く。
1秒でも「正確に速く」解ける「問題」が増える「春」にして欲しい。
家での勉強時間を少なくしたいなら、塾の授業中、隣の女の子や気になる男の子の顔を追いかける、大好きな「推し」と机の下のスマホで楽しむ時間をこの春だけちょっとやめてみたらええんやないやろか。「勉強がきらい」な人こそ、まずは、本気で「塾」の「授業時間」だけは「本気」に取り組んでみることをお勧めするで。
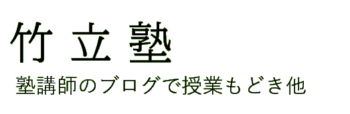
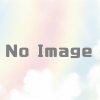
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません