きれいなノートはすべての生徒にとって正義ではない⑤
スタイラス、手書き
★★★「タブレット」での学習が主流になりつつあるが、一方で、TVでは毎年のように、よくスポーツ選手の「手書き」の「練習ノート」や「野球ノート」が登場する。自分を成長せるために「ノートを取る」。自分の字で「ノート」を書き、見直し、ページを重ねていき、やがてそれが「自己実現」につながっていく、そこに何か「ノート」の大切さがあるのではないだろうか…★★★
一時期、「書く」と言う「勉強法」に対して、「時間がかかる」「効率が悪い」「そんなことをするなら10回声に出して読めばいい」というような「偏った」考えが大流行したことがある。しかし、「何かを学ぶとき」、「音読だけ」「目で読むだけ」「耳で聞くだけ」では効果が薄いことはご承知の通りだ。さらに、その効果をを「答案用紙」に「点数」として表現するためには、明らかに「速く正確に、考え、計算し、書く技術」が必要なのだ。
「忘れないように」後で見直したときも「書いた時」の「臨場感」が残るような「ノート」。たとえ、「歴史」の人物や年号、「漢字」や「途中の計算」を覚えるために、殴り書きしたノートであっても、…それは「目的」をもって、自分の「字」で書かれた「自分の言霊で書かれた最強のアルバム」だ。「ノート」にはそんな「醍醐味」があるのではないだろうか。だからこそ、「書いて」確認したこと、練習したことが本番でできなかったとき、「くやしさ」が残る…。
「書く」という動作に対し、社会人になっても、あの時、「ノートやメモ」を残しておけば…ということも多々、日常生活でも出てくる。たとえ、「きれいなノート」ではなくても、後になっても分かる「最低限読める、分かるメモ」の延長線上に「自分のノート」がある、と言っても過言ではないだろうと思うんや。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
タブレットの登場により、より「書くこと」への意識がメッチャ薄れてきているように思う。生徒たちは「書き順」にこだわらなくなり…「。」を使わないメールが上空を飛び交う。当所、「きれいな字が打て」「訂正が可能なワープロ機能」に魅了され、「絵文字」によって「心」を支配され(言葉で表現するより、それにぴったりの絵文字をさがす人が多くなった)、ついには、「句読点」が怖いという時代を迎えた。「。」は「捨て台詞」「きつい態度」「ガチャ切り」のような感覚を受けるのだろうか。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ある時、自分の塾でも、「書く」ということに対し、「衝撃」的な事件が起こったので紹介したい。それは、前触れもなく突然、やってきた…
自分の教室に新しく入ってきた中1生の女の子に授業をしていた時のことだ。白板で授業を勧めていると…なんと、その子は、ノートを見ずに、頭を固定したまま「目」で板書を追って手をシャカシャカしながらノートに書きこんでいたのだ。「白板を写している」と言えるかどうかは分からない…お分かりいただけるだろか。彼女は、白板だけをガン見したまま(読んだり確認したりしないまま)ノートを見ずに、手だけ動かして「ノートを取る」特技を持っていたのだ。頭は上下動せず、白板だけを見ている。不思議なことに、字や数字はまっすぐに書かれていた…確かにノートを取るのは速い、しかし案の定、意識せずに手だけ動かしているため、ほとんど覚えていなかった。ある意味、特殊な能力である。
正直、最初はどうなることか、と思ったが、彼女も無事「高校合格」を決めてくれた。ある日、駅前のコンビニでバイトをしている彼女を発見。北海道で母の世話をすることになっていたため、高校の勉強は見てあげられなかったが、元気に笑顔で働いている姿を見て、ほっとしたことを思い出す。
★★★「勉強」の際、「まとめのノート」を作るときであっても「問題演習」をしているときであっても、「見ているものや書いたものを暗記するとき」でも、一つの「能力」だけを使っているわけではない。「見て覚える」のが得意、「聞いて覚えるのが得意」「口に出して覚えるのが得意」「書いて覚えるのが得意」…個人差があるが、やっていないことで、「勉強」の能力が上がる可能性があるのであれば、試す価値があるのではないだろうか。★★★
「10回読む」時は明らかに「目で確認し」「口を動かし」「自分の声を耳で聞き」「脳で判断する・考える」という動作が連動する。「ぼーっと見ているだけ」「眺めているだけ」で読んだ気になったり、「ただ回数を気にして、字面を追いかけて音読」していても当然、頭に残らない。
例えば、英語が得意なら、英語の教科書を
①「1回目は黙読し、分からない単語や発音できない単語をチェックする」…調べた後、
②「2回目は、訳を考えながら黙読する」…訳が分からない文に下線を引く…
③「3回目は音読してうまく言えない文をチェックする」…単語の発音が原因なのか、長い文なので、切れ目が分からないのかなどをチェックし、練習する…
④「4回目は、音読し終わったら、一文一文和訳してみる、先ほど下線を入れた文を単語が分からないのか、前後の文から推測できないか、文型を考えながら試訳する。…「5回目の音読後、自分の和訳したものを見ながら教科書本文を英語で書いてみる」
…当然、こなせれば成績は伸びる。しかし、「時間がない」のを理由にどこかで必ず止まってしまう生徒が9割以上だ。
「今時、訳や単語の意味がチェックできない」なんて言うキミはただの「面倒くさがり屋」だ。「ネット」にも教科書の訳や単語は転がっている。中学校や高校の学校の先生の訳や説明と「教科書ガイド」や「ネットの訳」が異なる場合は、それを、先生に質問すればよいだけやもん。
★「教科書な・ん・て役に立たない」と思っている生徒は多いが、その教科書に載っている文章すら「音読できない」「和訳できない」、教科書の「章末問題」どころか「例題」や「類題」が解けないまま「入試」を突破しようとする生徒が何と多いことか。
「教科書が読めない子供たち」「計算ができない大学生」という「フレーズ」が話題になって久しい。思うに、「かったるい」「時間がかかる」「どうせ同じ問題は入試に出ない」などを理由に生徒たちは「教科書」を読んだり、「自分で解く」ことを避けているように思う。
最近はあまり聞かないが、一時期、大学入学後、「高校の勉強の補習」をする大学が多かったように思う。「基礎科目」や「レポート」の書き方をで困らないよう、高校時代までに「時間内」で「解ける問題」を増やし、「要約」「エッセイ」を書く準備をしておくことが必要だが、誰もそんなことは教えてくれない。大学の「学部」によっては「物理」や「微積」が必要になる。受験時だけではなく、入学後の勉強する科目にも注意を向ける必要があるんで注意してな。
よく言われるように、「数学」の場合、教科書」は「基本」なのではなく、単なる入試への「入場券」なんよ。「教科書の章末問題」がスラスラできるレベルで「定期テスト」がそこそこの点数が取れ、「4ステップ」などの「教科書準拠の問題集」が完璧ならいきなり「入試用問題」にチャレンジしてみてもよいか、というレベルだと思うで。
「塾」や「予備校」などで「学校の単元」を先に勉強するときであっても、「塾のテキスト」を使うのであって「教科書」を使って講義する塾は稀だ。なぜ、塾で学校の「教科書」を使わないのか?ま、「講習会」などの短い期間で「集中的」に勉強を済ます、「塾教材」としての特別感を出すためなんかに必要なんやろね。「教材費」も稼げるし。
自分が、3件目に勤めてた塾長も、自分と同じこと言うとったで。「センセ、結局、教材なんてなに使ってもいいんですよ、大切なのは、教える『人』だよね」と。
塾の「教材費」については、詳しく触れることはここでは避けるが、「ワーク」や「テキスト」は、塾生の人数によって割引きはあるが、1冊の「仕入れ額」は、「1000円」以下のことが多い。それを「2000円~3000円」の教材費にして取っている塾が多い。ちなみに塾教材の種類によっては(例えば「全国入試問題集」のようなもの)、「アマゾン」で3000円~5000円で購入可能なものが多い。ネットやオークションで購入する時には、「解答」がついていない場合が多いので、必ず「解答付き」がどうか確認の上購入したらええ。
ここで、「英語」の「コミニケーション」の「教科書」を考えてみよう。おそらく、高校2年生程度の「コミの教科書」をスラスラ「音読」し「和訳や読み書き」できる生徒はほとんどいないだろう。おそらく、「全文英作」や「全文訳」を問題にした場合、「満点」を取る、となると、教師や塾の講師でもそんなに簡単ではないはずだ。「現文」「古文」「漢文」の教科書ですら、高校生と一緒にすらすら読める「学生講師」は実際には、少ないのではないか。塾講師に「予習」が必要な一つの理由がここにある。前にも書いたと思うが、予備校講師は、一コマに対し、最低授業の3番の時間をかけて予習をするそうだ。
余談ではあるけど、授業直前に手ぶらで来て、「赤い答えが載っとる」テキストを見ながら足を組んで解説する「学生講師」がいる塾にはワイは自分の子がいたら通わせんで。
だからこそ、今、左側に英文(上段に古文や数学の問題)、右側に日本語、解説型(下段に現代語訳と解説や数学の解答)の「ノート」が見直される必要がある、と自分は感じている。与えられる勉強ではなく、自分で「分からないところ」に気づくためにも、な。
実際に、大学進学率の高い私立の高校では、このタイプのノートの指導をしている学校もある(指導内容が多いので、穴埋めだらけのプリントを使用している学校もあった)。「書く」という勉強の方法の効果をまだ経験したことのない生徒には、ぜひ、トライしてみて欲しいと思う。
東京の私立高校の進学コースに通うある女子生徒がいたんや。テスト前、「教科書全文並べかえプリント」を作成して解かせていた時のことだ。「センセ、これ、ウチ自分で教科書を写して訳を確かめるよ」と言い出した。もともと「コミュニケ―ジョン」のテキストは「本文」が「定期テスト」に出るのに「音読」どころか、「黙読」もしない生徒ばかり(ほとんどの生徒は単語や熟語のチェックで終わってまう)なので、「内容と文法、語順、表現」を確かめさせる意味で「整序」のプリントを用意することが多かった。「ウチ、本気でやるよ」と彼女の目が訴えていたので、その時から、「コミ英」の対策授業はやめた。その後、彼女は各学期の「評定」「8」「9」と安定した成績を卒業するまで取っていた。彼女が作っていたのは、「完全版ノート」ではないが、単語のミスや文法に気を付けながら一文一文丁寧に「書く」ことが点数につながった成功例だと思う。
学校で「ノート」を提出させられる場合もあるだろう。「ノート」は「作ったら使え」である。右側だけを見て、左側の英文が言えるか、言えない場合や書けない場合は何が問題なっているか。「時制か、三単現や複数形、不可算などの数の問題か、それとも副詞の位置や文型の理解の問題」それとも「語順の問題」なのか。あるいは「単語」の発音やスペリングの問題なのか。
★「教科書」や「課題」を生徒と音読する、「教科書の内容を掘り下げて」生徒に白板で解説する、と言う話をすると、同僚の塾の先生たちは、「気持ちは分かるが、そんな時間はないよ。先生」と言われてしまう。果たして本当だろうか。
実際に、「二次方程式の解の公式を導け」「余弦定理を証明せよ」「三平方の定理を証明せよ」などの問題は、高校入試、大学入試でもちょいちょい出てくる。教科書の内容は理解しといたほうがええで。
3件目の塾では、よく「お帰り問題」で「教科書の音読」をさせとった、「1P」であっても丸ごとスラスラ読むことが難しい生徒もおる。1回で「合格」できひん生徒たちは、英語が得意な生徒に「単語の発音」や「フレーズ」の確認をして2回目、3回目にチャレンジしとったで。
「自分の塾」では、中学生、高校生の「夏休みの宿題」を必ずチェックしていた。中学校や高校では、夏休み明けのテストで、その宿題の内容が出題されることが多かったからだ。「数学」が苦手な生徒は、数学の宿題などは、計画を立て、生徒が解けない問題を見る時間を作る必要があった。
「課題」の中に、「読書感想文」や「英語の和訳」も出てくる。自分は、「感想文」や「和訳」の課題が学校から出された場合、一週間以内に「その本」を手に入れる。そして、1週間経ったころに「どこまで読んだ」と生徒に聞く。内容について何も答えられないようなら、本を持ってくるように指示し、次の授業から、1回15分~20分程度、交代で「音読」するための時間にあてた。
夏に夏目漱石の「こころ」を何人の生徒と読んだことか。ある時は英訳版の「バースデイガール」を1冊読み上げた。当然、英語の「音読」もした。その際、自分がこの英文が気に入った、この出来事に感動したという部分を『ノート』に書かせ、英文を写させた。次の回までに、感想や疑問などを書いてきてもらう。感想文を英語で書く場合は、日本語でまず考えて英語で文を作ってももちろん良いが、その際、自分が気になった部分をまとめるにあたって、英語で「気に入った文」や「表現」などをメモを残しておいた方がより書きやすい。英語で感想文に挑戦した生徒は、英語の発音はあまり得意ではなかったが、授業中、指されれば臆することなく英語で受け答えをしたし、学校の定期テストではもちろん、成績に困るようなことはなかった。
★さて、「過去問を答えを覚えてしまうくらいやる」の本当の意味をキミは知っているだろうか。「先生、ウチ、昨日、去年の問題90点取れたよ」生徒の8割は「答えの記号や数字を覚え」「記述の解答を丸暗記し」「途中の計算を手を動かさずに済ませ」答えだけを解答欄に書いている。「過去問の答えを覚えてしまうくらいやる」というのは、そういうことではない。
例えば、将来、大学の「看護学部」を目指したいなら、高1で学ぶ「数学」から手を抜いてはいけない。「薬学部」を目指すためには「数学」だけではなく「化学」ができた方が断然いい。
「模試」でききなかった問題も大切だが、「それ以前」の知識や問題演習が必要なら、まず、学校から配布された「4STEP」や「セミナー〇●」などの問題集をさらった方がいい。高3生で、時間がなく、どうしても「過去問」にこだわるのであれば、志望校の「過去10年分」までさかのぼるとか、似たような問題を出題する大学の赤本の演習をし、自分の間違えた問題を集めた「弱点ノート」を作ると有効だ。自分でできない場合は、塾の先生にも協力してもらおう。問題はコピーでも構わないが、復習のとき、問題と解答・解説は同時に見えないように工夫したノート作りが必要だ。なぜなら、自力でヒントなしで「デキるまで」練習する必要があるからだ。
一度間違えた問題を「ノーヒント」で「解答に書ける」つまり、「正解できる」生徒は本当に数少ない。一度ぐらい写す、見るだけではまず、1か月後、2か月後には解けなくなっているのが普通だ。本番は、まだ、「解答欄」に「書く」のがスタンダード。だとすれば、「時間内に書く」ことができなければ、落ちることになる。
中学生、高校生の中には、科目に関わらず、「先生、去年の入試問題、ウチ90点取れました」と講師室に報告に来る塾生がいる。その気持ちに「ほんとか~、それって答え覚えただけじゃね」と、水を差すのは悪いので、「じゃあ、同じような問題集めて過去問を作ってあげるから解いてみな」と言うと、たいていの生徒は「挑戦」を避け、机の前から去っていく。
彼らのほとんどが、「答えを覚えて」いるのだ。よく、「答えを覚えるくらい過去問をこなしなさい」という先生がいるが、自分はあまり感心しない…「具体的な指示」や「生徒への問いかけ」が欠けているからだ。「選択肢であれば、どの選択肢のどこが間違えていて、正答との違いは何か」、「(1)ではまず何を求めて、その答えを(2)にどう活かすのか」「なぜその公式を使うのか」「答えになるの根拠の文、表現はどこにあるのか」などなど。
地理であれば、選択肢の答えが「北海道」であるならば、「勘で当てた」「答えを覚えてしまっていた」は論外だ。北海道の自然・産業・歴史のなど選択肢のどこで判断したのか。他の3つの選択肢はそれぞれ「何県」なのか。
「(現代)国語」の「要約の選択問題」であれば、他の選択肢のどこが筆者の主張と違っているのか。違った部分は実際に筆者はどのように書いているのか、「選択肢が『本文の言い換え』の表現になっている場合」、それが正しいと判断した根拠は、本文中のどこか。
中学生や高校生の皆さんには、次につなるがるよう、その「模試」や「定期テスト」からできるだけ多くのことを学んで欲しい。
★「古文」や「漢文」ならともかく、「現文」の教科書を「丸写し」しなさい、と言われたら、おそらく9割の生徒は、「面倒くせえ、そんなことに何の意味があるんだよ?時間の無駄でしょ」と言うだろう。しかし、そこには、「キミの能力を開発しちゃう」案外すごいものが潜んでいることがある。自分は、「国語系」の教科は、ノートの上半分に「教科書本文」、下半分に問題や授業中の解説を書いていた。それだけで、結構「満足のいく点数」を取っていたのだ。その行為に、隠れている効能とは…
①「書くのが速くなる」(ある程度リズムに乗って書かないとテスト前に終わらないし、汚ければ後で読めない…適当に読める字で早く帰るようになる。また、視野が広くなり、『句読点』までを一気に目に覚えさせ、書く力がついてくる)
②「テスト範囲の漢字を少なくとも一回以上は練習できる」(漢字の部分が傍線部で直接テストに出題されるケースなら大ラッキー。ただし、写すときも「正確に」「速く」書くことが条件)
③「きちんと読みながら写せば、接続詞や穴埋めなどの問題は解きやすくなる」(字数指定であっても手が覚えていれば、答えをが一瞬でよみがえることも)
④「少なくとも、今の中学生・高校生よりはおそらく、文章が上手いと思われる作者・筆者の文章を勉強できる」(作家になりたい人は、好きな作家の文章を写して勉強したり、外国の作家が書いたものを訳したりして勉強する人もいる)
⑤何よりも、読んでいる、書いているのでテスト範囲の内容がある程度理解できるし、書いたという充実感もある(これは、付録みたいなものだが、一番、役に立つかもだ。意外と一回読んだ、それを書いたという不思議な自信がわいてくる)
⑥時間に余裕があれば、学校のノートやワーク、先生の解説やネットに載っている「過去問」などを使って自分で「予想問題」を作成できる
これで、点数が安定してくれば、他の教科で勉強で追われているときに、「とにかく現文は、教科書を一回写せば何とかなる」という妙な自信が自分を支えてくれる。ちなみに、「予習段階」で本文を「写しておくと」授業がより聞きやすくなるし、テスト前に慌てなくてすむ。今でも自分は、「小説」などで「これ、いいわ~」と思った文は、ノートに写すのがクセになっている。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
まあ、時間がない、どうしても「書く気」になれない人は無理しなくてもええけど…一度トライしてみたい人はぜひやってみてな。もちろん、自分の勉強法を持っとる人は、自分のやり方で「入試」を「突破」したらええ。
★ここまで読んでいただきありがとうございました。このタイトルの記事、続きを出すのに思いのほか、時間がかかってしまいました。今から、また、校正タイムに入ろと思います。次回は「国語の記述の答えへのアプローチ」「小学校の算数の重要性」などに触れつつ「ノート」ちゅう話題とからめていこか、と思っています。また、読んでいただけるとありがたいです、では。
、
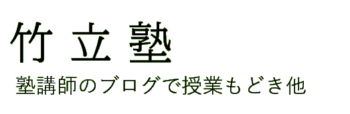
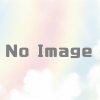
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません